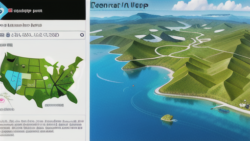所得補償保険
所得補償保険 遺族年金:大切な遺族を守る備え
遺族年金とは、家族の大黒柱を失った遺族の暮らしを支えるための大切な公的制度です。国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その人の収入で生計を立てていた家族に支給されます。これは、突然の収入減による生活苦を防ぎ、遺族が安心して生活を立て直せるようにするためのものです。
遺族年金には、大きく分けて三つの種類があります。一つ目は、国民年金に加入していた人の遺族のための遺族基礎年金です。二つ目は、厚生年金に加入していた人の遺族のための遺族厚生年金です。そして三つ目は、国家公務員や地方公務員などの共済組合員であった人の遺族のための遺族共済年金です。これらの年金は、亡くなった人が加入していた制度や遺族の状況によって、支給額や支給されるための条件が違います。
遺族基礎年金は、故人が一定期間以上国民年金に加入していた場合に支給されます。支給額は、故人の年金の加入期間や遺族の人数によって決まります。子供がいる場合には、子の加算額が支給されます。遺族厚生年金は、故人が一定期間以上厚生年金に加入していた場合に支給されます。支給額は、故人の平均標準報酬額や遺族の人数によって決まります。遺族基礎年金と同様に、子供がいる場合には、子の加算額が支給されます。遺族共済年金も、故人の加入期間や遺族の状況によって支給額や支給要件が異なります。
遺族年金は、亡くなった人が積み立てた年金の一部が支給されるのではなく、社会全体で支え合う仕組みのもとで支給されるものです。ですから、亡くなった人が年金保険料を支払っていなかった場合でも、一定の条件を満たせば遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金は、大切な家族を亡くした遺族にとって、生活の支えとなる重要な制度です。もしもの時に備えて、制度の内容をよく理解しておくことが大切です。詳しくは、お近くの年金事務所や市区町村役場にお問い合わせください。