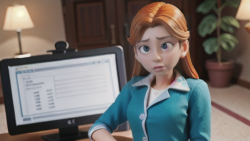その他
その他 社員配当金とは?仕組みとメリットを解説
社員配当金とは、生命保険会社が相互会社である場合に、契約者(社員)に支払われるお金のことです。生命保険会社には株式会社と相互会社という二つの形態があります。株式会社は株主が所有者となりますが、相互会社は契約者自身が所有者となります。つまり、生命保険に加入することで、契約者はその会社の社員としての権利を持つことになります。
社員配当金は、会社が一年間の事業を終えた後の決算で黒字になった場合、その一部を社員に還元する形で支払われます。この黒字の部分を剰余金と言います。剰余金は、主に集めた保険料を運用して得た利益や、事業にかかる費用を節約することで生み出されます。たとえば、予定していたよりも事務作業にかかる費用が少なかった場合などは、剰余金が増える要因となります。つまり、社員配当金は、会社全体の業績が良い時に、社員である契約者にもその成果が分配される仕組みです。
配当金の額は、契約している保険の種類や、保険金額、そして会社の業績などによって変わります。例えば、同じ保険会社でも、医療保険と死亡保険では配当金の額が異なることがあります。また、同じ種類の保険でも、保障の金額が高いほど配当金も高くなる傾向があります。さらに、会社の業績が良いほど、剰余金も増えるため、配当金の額も多くなる可能性があります。
ただし、配当金の支払いは必ず毎年行われるとは限りません。会社の業績によっては、剰余金が出ない場合もあります。その場合は、配当金は支払われません。配当金は会社の業績に連動するため、配当額の変動も起こりえます。
このように、社員配当金は会社の業績次第で支払われるかどうか、そして金額も変動しますが、契約者にとっては嬉しい収入となることが多いです。生命保険への加入を検討する際には、社員配当金の有無や仕組みを確認しておくことが大切です。