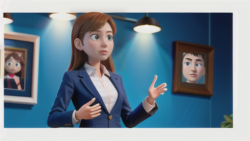自動車保険
自動車保険 保険事故と等級の変動について
保険契約を結ぶということは、万一の出来事に備えて経済的な支えを得るためです。では、一体どのような出来事が起きた時に、保険会社は私たちにお金を出してくれるのでしょうか。それを理解するために重要なのが「保険事故」という言葉です。保険事故とは、契約している保険の種類に応じて、保険会社が保険金や給付金を支払う義務が生じる出来事を指します。
例えば、自動車を運転中に、うっかり電柱にぶつかってしまい、電柱と自分の車が損傷してしまったとしましょう。もしあなたが自動車保険に加入していれば、電柱の修理費用やあなたの車の修理費用を保険会社が負担してくれるかもしれません。これは、事故によって損害が生じたこと、そしてそれが契約している自動車保険の保障範囲内であることから、保険事故として認められるためです。
また、自転車に乗っている時に転倒し、相手に怪我をさせてしまった場合も考えてみましょう。もしあなたが個人賠償責任保険に加入していれば、相手の方の治療費や慰謝料などを保険会社が負担してくれる可能性があります。これも相手に怪我をさせてしまったという事故が、個人賠償責任保険の保障対象であるため、保険事故とみなされるからです。
このように、保険事故には物に対する損害だけでなく、人への損害も含まれます。さらに、病気やケガによる入院や手術なども、生命保険や医療保険の契約内容によっては保険事故として扱われます。つまり、保険事故の種類は、契約している保険の種類によって大きく異なるのです。自分がどのような場合に保険金を受け取れるのかを知るためには、保険証券をよく確認し、契約内容を理解しておくことが大切です。保険証券には、保障の範囲や保険金の支払い条件などが詳しく記載されています。万が一の際に慌てないためにも、日頃から自分の保険についてきちんと把握しておきましょう。