利差配当型保険を徹底解説

保険について知りたい
先生、「利差配当タイプ」と「3利源配当タイプ」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?

保険のアドバイザー
いいかい?簡単に言うと、お金が増える計算のもとになるものが違うんだ。「利差配当タイプ」は「予定利率」だけを基にしている。つまり、お金を貸した時の利息でどれだけ増えるかだけで計算しているんだよ。一方、「3利源配当タイプ」は「予定死亡率」「予定利率」「予定事業費率」の3つを基に計算している。つまり、亡くなった人の数や会社の経費なども計算に入れているんだ。

保険について知りたい
なるほど。計算のもとになるものが違うんですね。でも、それによって何が変わるんですか?

保険のアドバイザー
配当金をもらえるかどうか、そして、いつからもらえるかが変わるんだよ。「利差配当タイプ」は契約から6年目以降、5年ごとにもらえる。「3利源配当タイプ」は契約から3年目以降にもらえる可能性があるんだ。3利源配当タイプの方が早く配当金を受け取れる可能性があるということだね。
利差配当タイプとは。
生命保険には、お配り金があるタイプとないタイプがあります。お配り金があるタイプには、「利息の差額で配当が決まるタイプ」と「3つの要素で配当が決まるタイプ」があります。「利息の差額で配当が決まるタイプ」は、あらかじめ決めた利息と実際の利息との差額に応じてお配り金がもらえるものです。お配り金は、契約から6年目以降、5年ごとにもらえます。「3つの要素で配当が決まるタイプ」は、毎年の決算時に、あらかじめ決めた死亡する人の割合、利息、事業にかかる費用と、実際の値との差額に応じてお配り金がもらえるものです。お配り金は、契約から3年目以降にもらえます。
配当型とは
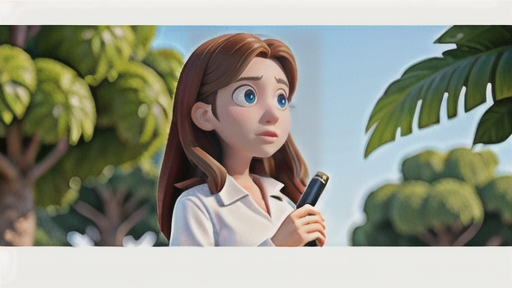
生命保険には大きく分けて、契約者に配当金が支払われる「配当型」と、配当金がない代わりに保険料が抑えられた「無配当型」の二種類があります。
配当型は、集めた保険料の一部を運用し、その運用益に応じて契約者に配当金を還元する仕組みです。将来の経済状況によって配当金の額は変動し、場合によっては全く支払われない可能性もありますが、運用が好調であれば、より多くの配当金を受け取れる可能性を秘めています。
一方、無配当型は配当金は支払われませんが、あらかじめ保険料が割安に設定されています。そのため、将来の経済状況に左右されることなく、一定の保険料を払い続けることができます。
配当型には、「利差配当型」と「3利源配当型」の二種類があります。利差配当型は、予定利率と実際の運用利率の差額から配当金を支払う仕組みです。一方、3利源配当型は、利差に加えて、予定された事業費よりも実際の事業費が少なかった場合の差額(費差)と、予定された死亡率よりも実際の死亡率が低かった場合の差額(死差)からも配当金を支払います。
どちらのタイプが自分に適しているかは、将来の不確実性に対する考え方や収益への期待によって判断する必要があります。将来の収入や支出を確実に予測し、安定した保障を確保したい方は、無配当型が良いでしょう。多少の不確実性を許容し、将来の運用益による上乗せに期待したい方は、配当型を検討すると良いでしょう。
自分に合った保険を選ぶためには、それぞれのメリット・デメリットを理解し、将来のライフプランを踏まえてじっくりと検討することが大切です。

利差配当型の仕組み

利差配当型は、将来の運用実績に応じて配当金が変動する生命保険商品です。この仕組みを理解する上で重要なのは、「予定利率」と「実際の運用利率」という二つの利率です。
まず、予定利率とは、保険会社が契約時に将来の運用利率を予測し、あらかじめ設定する利率のことです。この利率は、保険料の算出や保険金、解約返戻金の額を決める基礎となる重要な数値です。いわば、保険会社が契約者に対して最低限保証する利率とも言えます。
次に、実際の運用利率とは、保険会社が契約者の保険料を運用して実際に得た収益率のことです。保険会社は、集めた保険料を国債や社債、株式などの様々な資産に投資し、運用益を得ています。この実際の運用利率は、市場の金利変動など様々な要因によって変化するため、契約時に正確に予測することは困難です。
利差配当型保険では、この実際の運用利率が予定利率を上回った場合、その差額が剰余金として積み立てられます。この剰余金の一部、もしくは全部が契約者に配当金として支払われます。つまり、保険会社が運用をうまく行い、高い収益を上げた場合は、その成果が契約者に還元される仕組みとなっています。
一方、実際の運用利率が予定利率を下回った場合、配当金は発生しません。しかし、保険金や解約返戻金の額は、あらかじめ設定された予定利率に基づいて計算されるため、減額されることはありません。予定利率が最低保証の役割を果たすため、運用が芳しくなくても、契約者は予定利率に基づいた金額を受け取ることができます。
このように、利差配当型は将来の金利情勢の見通しが明るい場合に有利となる可能性があります。ただし、実際の運用利率は市場環境に左右されるため、配当金は保証されていません。将来の金利動向を慎重に見極めた上で、加入を検討することが大切です。
| 項目 | 説明 | 役割 |
|---|---|---|
| 予定利率 | 保険会社が契約時に設定する将来の運用利率の予測値 | 保険料、保険金、解約返戻金の算出基礎。 契約者への最低保証利率。 |
| 実際の運用利率 | 保険会社が実際に運用して得た収益率 | 剰余金の発生源 (実際の運用利率 > 予定利率の場合) |
| 配当金 | 実際の運用利率が予定利率を上回った場合に、その差額の一部または全部が契約者に支払われる | 契約者への運用成果の還元 |
配当金の受取時期

生命保険の契約には、利差配当型と呼ばれる種類があり、契約から一定期間が経過すると、配当金を受け取ることができます。この配当金は、保険会社の運用実績に応じて支払われるもので、受け取り時期や方法は契約によって異なります。
多くの場合、利差配当型の保険では、契約から6年が経過した後に初めて配当金を受け取ることができます。その後は、5年ごと、つまり11年目、16年目というように配当金の受け取り時期が到来します。
受け取った配当金の使い道には、いくつかの選択肢があります。一つ目は、現金で受け取る方法です。受け取ったお金は自由に使うことができます。二つ目は、将来支払う保険料に充てる方法です。この方法であれば、将来の保険料負担を軽減することができます。三つ目は、配当金を積み立てて運用し、将来まとめて受け取る方法です。この方法では、複利効果によって配当金を増やすことが期待できます。
どの方法が最適かは、加入者の生活設計やお金の計画によって異なります。例えば、まとまったお金が必要な時期がある場合は、積み立てて運用する方法が適しているかもしれません。逆に、家計の足しにしたい場合は、現金で受け取る方法が適しているでしょう。将来の保険料の支払いが負担になりそうな場合は、保険料に充てる方法も有効です。
保険会社によって、配当金の受け取り時期や方法、運用方法などが異なる場合があります。そのため、契約を検討する際は、各社の資料をよく読んで比較検討し、不明な点は担当者に確認することが大切です。契約後に後悔することがないように、契約前にしっかりと理解しておくことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険の種類 | 利差配当型 |
| 配当金開始時期 | 契約から6年後、以降5年ごと |
| 配当金の受取方法 | 1. 現金受取 2. 保険料充当 3. 積み立て運用 |
| 各受取方法のメリット | 1. 現金受取:自由に使える 2. 保険料充当:将来の保険料負担軽減 3. 積み立て運用:複利効果で増える |
| 最適な受取方法 | 加入者の生活設計やお金の計画による |
| 注意点 | 保険会社によって異なる場合があるため、資料をよく読んで比較検討し、不明な点は担当者に確認 |
3利源配当型との違い
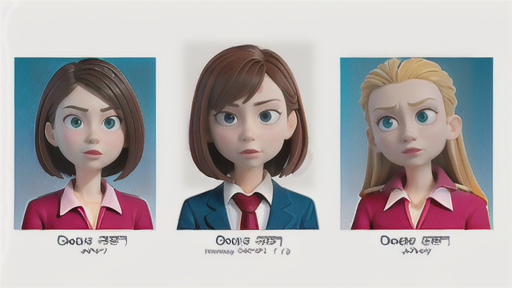
三大源配当型は、利差配当型に加えて、死亡率や事業費率の差からも剰余金が発生し、それが配当金に反映される仕組みです。この三大源配当型と利差配当型の違いについて詳しく見ていきましょう。
利差配当型は、主に運用実績によって生まれた利益、つまり予定利率と実際の実績利率の差から剰余金が発生します。一方、三大源配当型は、この利差に加えて、死亡率の差と事業費率の差からも剰余金が発生します。死亡率の差とは、あらかじめ予定していた死亡率と、契約者全体の実際の死亡率との差を指します。例えば、予定より実際の死亡率が低い場合、支出が抑えられ剰余金が発生します。また、事業費率の差とは、あらかじめ予定していた事業費率と、実際の事業費率との差です。保険会社が事業運営にかかった費用が、予定より少なかった場合に剰余金が発生します。
このように、三大源配当型は利差配当型に比べて剰余金の発生源が多いため、より多くの配当金を受け取れる可能性があります。ただし、配当金の額は、将来の運用実績や死亡率、事業費率によって変動するため、必ずしも多く支払われると保証されたものではありません。また、三大源配当型の商品は、配当金の支払いが開始される時期が契約から3年目以降となる場合が多く、すぐに配当金を受け取れるとは限りません。
三大源配当型は、複数の要素から剰余金が生み出されるため、相対的に安定した配当が期待できるというメリットがあります。しかし、配当金は保証されたものではないため、将来の不確実性を理解した上で加入を検討することが大切です。
| 項目 | 利差配当型 | 三大源配当型 |
|---|---|---|
| 剰余金の発生源 | 予定利率と実際の実績利率の差 | 予定利率と実際の実績利率の差 予定死亡率と実際の死亡率の差 予定事業費率と実際の事業費率の差 |
| 配当金 | 剰余金から発生 | 剰余金から発生 |
| 配当の特徴 | 運用実績に大きく依存 | 複数の発生源による相対的な安定性 |
| 配当開始時期 | 記載なし | 契約から3年目以降が多い |
保険選びのポイント

人生における様々な出来事、例えば結婚、出産、住宅購入、子供の教育、そして老後の生活など、将来設計を考える上で、お金の備えは欠かせません。その備えとして、生命保険は重要な役割を担います。しかし、数多くの保険商品の中から、自分にぴったりの保険を選ぶことは容易ではありません。そこで、保険選びで失敗しないためのポイントをいくつかご紹介します。
まず将来の生活設計を具体的に描いてみることが大切です。結婚、出産、住宅購入、子供の教育、老後など、人生の節目で必要となるお金はどれくらいなのか、大まかにでも見積もってみましょう。現在の収入と支出のバランスを把握し、将来発生するであろう支出に備えられるか、不足する場合はどの程度なのかを具体的に検討することで、必要な保障額が見えてきます。
次に保険の種類を理解しましょう。大きく分けて、死亡時に保険金が支払われる死亡保険、病気やケガで入院した際にお金が受け取れる医療保険、そして老後の生活資金を準備するための年金保険などがあります。それぞれの保険の特徴を理解し、自身のニーズに合った保険を選ぶことが重要です。例えば、お子さんが小さいうちは死亡保障を厚くし、教育資金が必要な時期には学資保険を検討する、といったように、ライフステージに合わせて保障内容を見直すことも大切です。
さらに、保険料の支払方法や保険期間も重要な要素です。保険料は毎月支払うのか、まとめて支払うのか、また保険期間は一生涯なのか、一定期間なのかなど、様々な選択肢があります。自身の家計状況や将来設計に合わせて、無理なく続けられる支払方法と期間を選ぶようにしましょう。
保険を選ぶ際には、複数の保険会社の商品を比較検討することも重要です。同じような保障内容でも、保険料やサービス内容が異なる場合があります。複数の保険商品を比較し、保障内容、保険料、サービス内容などを総合的に判断することで、より自分に合った保険を見つけることができます。
最後に、保険の専門家に相談することも有効な手段です。専門家は、様々な保険商品に関する知識や経験が豊富です。自身の状況やニーズを伝え、適切なアドバイスを受けることで、より安心して保険選びを進めることができるでしょう。保険は複雑な商品であり、内容を完全に理解することは難しい場合もあります。専門家の力を借りることで、よりスムーズに、そして自分に最適な保険を選ぶことができるでしょう。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 将来の生活設計 | 結婚、出産、住宅購入、子供の教育、老後など、人生の節目で必要となるお金を大まかに見積もり、現在の収入と支出のバランスを把握し、将来発生するであろう支出に備えられるか、不足する場合はどの程度なのかを具体的に検討する。 |
| 保険の種類の理解 | 死亡保険、医療保険、年金保険など、それぞれの保険の特徴を理解し、自身のニーズに合った保険を選ぶ。ライフステージに合わせて保障内容を見直す。 |
| 保険料の支払方法と保険期間 | 保険料の支払方法(毎月、まとめて)や保険期間(一生涯、一定期間)など、自身の家計状況や将来設計に合わせて、無理なく続けられる方法を選ぶ。 |
| 複数の保険会社の商品比較 | 同じような保障内容でも、保険料やサービス内容が異なる場合があるので、複数の商品を比較し、保障内容、保険料、サービス内容などを総合的に判断する。 |
| 保険の専門家への相談 | 専門家に自身の状況やニーズを伝え、適切なアドバイスを受けることで、より安心して保険選びを進めることができる。 |
将来設計に合わせて

人生はまるで川の流れのようです。穏やかな流れの時期もあれば、急流となる時期もあります。結婚、出産、家の購入、子供の教育、そして老後と、人生の様々な場面で必要となるお金の額や種類は変化していきます。将来の生活設計をしっかりと考え、それに合わせて必要な備えを準備しておくことが大切です。
例えば、結婚を機に新しい家庭を築くことになれば、それまでとは違った保障が必要になります。配偶者や将来生まれてくる子供を守るための備えを検討する時期と言えるでしょう。また、住宅を購入する際には、大きな金額のローンを組むことになります。万が一のことがあった場合でも、家族が安心して住み続けられるよう、住宅ローンに合わせた保障内容の見直しが重要になります。
子供が成長するにつれて教育資金の必要性が高まります。大学進学など、大きなお金が必要となる時期に向けて、計画的に教育資金を準備するための貯蓄や保険を検討する必要があります。さらに、老後は現役時代とは異なり、収入が減少する一方で、医療費や介護費などの支出が増加する傾向にあります。ゆとりある老後生活を送るためにも、早いうちから老後資金の準備を始めることが大切です。
このように、人生の様々な転換期に合わせて、定期的に保険の内容を見直し、今の状況に合っているかを確認することは、安心して暮らしていく上で非常に重要です。保険は、予期せぬ出来事から私たちを守り、経済的な負担を軽減してくれる大切な役割を果たします。様々な種類の保険があり、それぞれに特徴があります。それぞれの保険の特徴をしっかりと理解し、自分の状況や将来の計画に合った保険を選ぶことで、より安定した生活を送るための土台を築くことができるでしょう。
| ライフステージ | 必要となるお金/備え | 検討事項 |
|---|---|---|
| 結婚 | 新しい家庭に必要な保障 | 配偶者や子供を守るための備え |
| 住宅購入 | 住宅ローン返済 | 万が一の場合の家族の住居確保のための保障(団体信用生命保険など) |
| 子育て | 教育資金 | 大学進学などに向けた計画的な貯蓄や保険 |
| 老後 | 医療費、介護費、生活費 | ゆとりある老後生活のための資金準備 |
