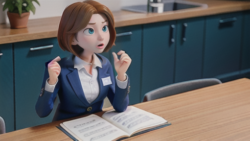税金
税金 減価償却:価値の減少を理解する
建物や機械、車両など、会社が仕事で使うものの中には、長い間使えるものがたくさんあります。これらを固定資産と言いますが、これらの固定資産は、使っているうちにだんだん古くなって価値が下がっていきます。例えば、真新しいトラックを購入したとします。購入当初はピカピカで最新の機能を備えています。しかし、毎日荷物を運んで何年も使い続けると、当然ながら傷やへこみができ、エンジンも劣化していきます。数年後には修理が必要になるかもしれませんし、新しい、より燃費の良いトラックも登場するでしょう。このように、固定資産は時間と共に劣化したり陳腐化したりして、その価値が徐々に減少していくのです。
この価値の減少分を、会計上きちんと処理する手続きが減価償却です。もし、トラックの購入費用を一度に全て経費として計上してしまうと、購入した年に大きな損失が出て、その後の年の利益が実際よりも高く見えてしまいます。これは、会社の本当の経営状態を把握する上で適切ではありません。そこで、減価償却を行い、トラックの価値の減少分を、そのトラックが使えるであろう期間(耐用年数)にわたって少しずつ経費として計上していくのです。
例えば、1000万円で購入したトラックの耐用年数が10年だとすると、1年あたり100万円ずつ経費として計上します。こうすることで、トラックを使ったことによるコストを、その使用期間全体に公平に配分できるようになり、会社の業績をより正確に反映した決算書を作成できます。また、減価償却によって計上された費用は、税金の計算上も経費として認められるため、節税効果も期待できます。このように、減価償却は会社の経営状態を正しく把握し、健全な経営を続ける上で非常に重要な役割を果たしているのです。