企業を守る!リスクマネジメント

保険について知りたい
先生、「リスクマネジメント」って、保険に入るだけのことじゃないんですよね?よくわからないのですが、教えていただけますか?

保険のアドバイザー
そうだね、保険はリスクマネジメントの一つの手段ではあるけれど、全体ではないよ。リスクマネジメントとは、会社が抱える様々な危険を把握し、それらへの対策を考えて実行していくことなんだ。危険には、お金の問題だけでなく、会社の評判が悪くなるといったものもあるんだよ。

保険について知りたい
なるほど。でも、危険っていつ起こるかわからないですよね?そうなると、対策も難しいんじゃないですか?

保険のアドバイザー
その通り。危険はいつ、どれくらいの大きさで起こるかわからないことが多い。だから、事前に色々な危険を想定して、その危険が起こる可能性を小さくしたり、実際に起こった時の影響を少なくしたりする対策を前もって考えておくことが大切なんだよ。
リスクマネジメントとは。
保険の言葉で『リスクマネジメント』というものがあります。会社を経営していく上で、隠れている色々な危険を見つけ出し、調べて、対策を考えていくことです。危険には不確かなことがつきもので、いつ起こるかは分かりません。予想外の危険もある上に、いくつもの危険が同時に影響し合うこともあります。このような状態にうまく対処していくための方法がリスクマネジメントです。危険が起こると、会社は必ず影響を受けます。お金の損害も出るため、保険を使って負担を軽くするというのも一つの方法ですが、危険そのものをなくすことはできません。リスクマネジメントでは、危険が起こること自体を防ぎ、お金以外の影響も減らしていくことが大切です。
リスクマネジメントとは

事業を営む上で、危険を管理する手法は事業の土台となる大切なものです。これは、広く「危機管理」と呼ばれ、会社組織の大小を問わず、事業活動を続ける限り、様々な危機と隣り合わせとなる宿命を負っているからです。思いもよらない出来事が起きた時、事業活動が滞り、最悪の場合、事業の継続が危ぶまれる事態も想定されます。危機管理の目的は、このような危険をあらかじめ見抜き、その大きさを測り、適切な対応策を講じることで、会社への悪い影響を可能な限り小さくすることです。
危機管理は、いくつかの段階に分けて行います。まず、隠れている潜在的な危機を洗い出し、特定します。次に、その危機が起こる可能性の高さと、もし起こった場合の影響の大きさを評価します。例えば、地震や火災といった自然災害、情報漏えいやサイバー攻撃といった情報セキュリティに関する事柄、従業員の不正行為や事故、取引先の倒産、法律の改正、競合他社の出現、原材料価格の高騰、顧客の嗜好の変化など、様々な危機が考えられます。これらの危機は、会社の種類や事業内容、置かれている状況によって大きく変わるため、自社にとってどのような危機が想定されるかを具体的に考えることが重要です。
危機の評価が終わったら、その危機を避ける、あるいはその影響を小さくするための対策を検討し、実行に移します。具体的には、保険への加入、代替供給元の確保、従業員教育の実施、情報システムの強化、危機対応マニュアルの作成などが挙げられます。
最後に、実行した対策がどれほど効果があったのかを検証し、必要に応じて対策内容を見直すことで、危機管理の精度を高めていきます。危機管理は一過性のものではなく、常に変化する状況に合わせて継続的に行う必要があるため、この検証と改善のサイクルを繰り返すことが大切です。このように、危機管理を適切に行うことは、会社の安定した成長に欠かせない要素と言えるでしょう。
| 危機管理の段階 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 危機の特定 | 潜在的な危機を洗い出し、特定する。 | 自然災害、情報漏洩、サイバー攻撃、従業員の不正行為、事故、取引先の倒産、法律の改正、競合他社の出現、原材料価格の高騰、顧客の嗜好の変化など |
| 危機の評価 | 危機が起こる可能性と影響の大きさを評価する。 | 発生確率、影響度を分析 |
| 対策の実行 | 危機を避ける、あるいは影響を小さくするための対策を実行する。 | 保険への加入、代替供給元の確保、従業員教育、情報システムの強化、危機対応マニュアルの作成など |
| 検証と改善 | 対策の効果を検証し、必要に応じて対策内容を見直す。 | 定期的な見直し、改善策の実施 |
リスクの種類

事業を行う上で、避けることのできない様々な危険が存在します。これらの危険は、企業活動に大きな影響を与える可能性があるため、種類を正しく理解し、適切な対策を準備することが大切です。大きく分けて、損失のみが想定される危険と、損失と利益の両方が想定される危険の二種類があります。
まず、損失のみが想定される危険は、純粋な危険と呼ばれます。何も対策を講じなければ、財産や人命に関わる大きな損害につながる可能性があります。代表的な例としては、火災、地震や台風などの自然災害、従業員が業務中に負うけがなどが挙げられます。このような純粋な危険に対しては、事前に発生を防ぐ対策を徹底することが重要です。例えば、防火設備の点検や防災訓練の実施、安全な作業環境の整備などが挙げられます。さらに、万が一の事態に備えて、損害を補填するための保険に加入することも有効な手段です。
次に、損失と利益の両方が想定される危険は、投機的な危険と呼ばれます。事業活動に伴う機会費用も含まれます。例えば、新しい事業への投資は、成功すれば大きな利益を獲得できますが、失敗すれば損失を被る可能性があります。また、為替の変動も、円高になれば輸入コストが減少しますが、円安になれば輸出競争力が低下する可能性があります。このような投機的な危険に対しては、利益を最大化するための計画を立てることが重要です。同時に、損失を最小限に抑えるための備えも必要です。例えば、複数の取引先を確保することで特定の取引先への依存度を下げたり、為替予約を活用することで為替変動の影響を軽減したりするなど、危険を分散させる工夫が重要となります。
このように、企業が直面する危険は多岐に渡ります。それぞれの危険の種類を理解し、危険の大きさや発生の可能性を分析した上で、適切な対策を講じることが、企業の安定した経営につながります。
| 危険の種類 | 内容 | 例 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 純粋な危険 (損失のみ) | 何も対策を講じなければ、財産や人命に関わる大きな損害につながる可能性がある危険。 | 火災、地震、台風などの自然災害、従業員の業務中のけが | 発生予防策(防火設備の点検、防災訓練、安全な作業環境の整備など)、保険への加入 |
| 投機的な危険 (損失と利益の両方) | 事業活動に伴う機会費用も含む。成功すれば利益、失敗すれば損失。 | 新規事業への投資、為替の変動 | 利益最大化のための計画、損失最小化のための備え(危険分散、為替予約など) |
リスク特定の手法
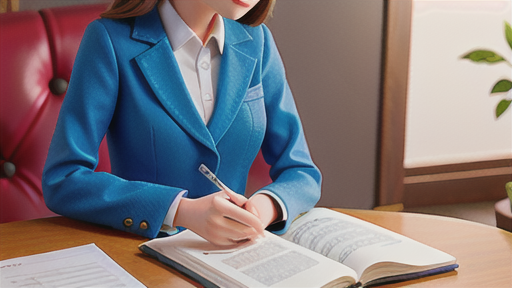
事業を成功させるためには、危険を見つけることがとても大切です。危険を早い段階で見つけることで、大きな損害を防ぎ、事業を順調に進めることができます。危険を見つけるには、色々な方法があります。これらの方法をうまく組み合わせて使うことで、あらゆる角度から危険を捉えることができます。
まず、過去の出来事を詳しく調べるという方法があります。過去の成功や失敗を分析することで、これから起こりそうな危険を予測することができます。例えば、以前同じような事業で失敗した経験があれば、その原因を分析し、同じ間違いを繰り返さないように対策を立てることができます。過去の成功事例からも、成功の要因を分析することで、新たな危険を回避するヒントを得ることができます。
次に、その道の専門家の意見を聞くという方法も有効です。社内だけでは気づきにくい視点や専門的な知識を持つ専門家から意見を聞くことで、自分たちだけでは見落としてしまう危険に気づくことができます。外部の専門家は、客観的な立場で状況を判断し、的確なアドバイスをくれるため、貴重な情報源となります。
さらに、あらかじめ用意した確認表を使うという方法もあります。確認表を使うことで、漏れなく危険を洗い出すことができます。確認表には、過去の事例や専門家の意見を参考に、起こりうる危険を網羅的にリストアップしておくことが重要です。確認表を用いることで、見落としを防ぎ、網羅的に危険を特定することができます。
危険は常に変化するものです。そのため、一度危険を特定したらそれで終わりではなく、定期的に見直しを行うことが大切です。事業を取り巻く環境や状況の変化に合わせて、新たな危険が発生する可能性があるため、常に注意を払い、定期的に危険の洗い出しと対策の見直しを行う必要があります。これらの方法を組み合わせて、多角的に危険を捉え、適切な対策を講じることで、事業の成功確率を高めることができます。
| 危険発見方法 | 説明 | 利点 |
|---|---|---|
| 過去の出来事の分析 | 過去の成功や失敗を分析し、将来の危険を予測する。 | 過去の経験から学び、同じ間違いを繰り返さないように対策できる。成功要因を分析し、新たな危険回避のヒントを得られる。 |
| 専門家の意見 | 専門家から助言を得ることで、見落としがちな危険に気づく。 | 客観的な視点と専門知識による的確なアドバイスを受けられる。 |
| 確認表の使用 | あらかじめ用意したリストで危険を洗い出す。 | 漏れなく危険を特定し、網羅的に対策を検討できる。 |
リスク評価

事業を滞りなく進めるためには、危険になりうる事柄を洗い出し、その危険度合いを測ることが欠かせません。これを危険度評価といいます。危険度評価は、危険が起こる可能性の高さと、その危険が実際に起こった場合の影響の大きさの2つの要素を基に行います。
まず、危険が起こる可能性の高さについてですが、これは、過去の出来事や似たような事業での経験、専門家の意見などを参考にしながら、どの程度の確率でその危険が起こるかを予測します。例えば、過去に何度も停電が起きている地域では、将来も停電が起こる可能性が高いと判断できます。
次に、危険が実際に起こった場合の影響の大きさについてですが、これも同様に、過去の出来事や専門家の意見などを参考にしながら、事業にどれだけの損害が出るかを予測します。例えば、工場で火災が発生した場合、建物や設備が焼失するだけでなく、生産が停止し、顧客への納品が遅れるといった大きな損害が発生することが考えられます。
これらの2つの要素を掛け合わせることで、それぞれの危険の大きさを数値で表すことができます。数値化することで、危険の大きさ比べができるようになり、どの危険に優先的に対策を講じるべきかを判断することができます。限られた資源を有効に活用するためにも、この優先順位付けは重要です。
危険度評価は一度行えば終わりではありません。事業を取り巻く環境は常に変化するため、定期的に見直し、必要に応じて修正していく必要があります。例えば、新しい法律が施行された場合や、新しい技術が導入された場合などは、危険度評価を見直す必要があります。このように、継続的に危険度評価を行うことで、事業の安定と成長を守ることができるのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 危険度評価の目的 | 事業を滞りなく進める上で起こりうる危険を洗い出し、その危険度合いを測ること |
| 危険度評価の要素 |
|
| 危険が起こる可能性の高さの評価方法 | 過去の出来事、類似事業の経験、専門家の意見などを参考に予測 |
| 危険が実際に起こった場合の影響の大きさの評価方法 | 過去の出来事、専門家の意見などを参考に、事業への損害を予測 |
| 危険度の数値化 | 可能性の高さ × 影響の大きさ |
| 危険度評価の目的 | 危険の大きさ比べ、優先順位付け、資源の有効活用 |
| 危険度評価の見直し | 事業環境の変化に応じて定期的に見直し、修正 |
リスク対策

事業を行う上で、危険を無くす、あるいは小さくすることはとても大切です。危険への備えとなる様々な方法を、危険の種類や会社の状態に合わせて上手に使うことで、会社の損失を少なくし、安定した経営を行うことができます。危険への備えには、大きく分けて四つの方法があります。
一つ目は、危険の芽を摘むことです。危険につながる行動を完全にやめることで、危険を根本から防ぎます。例えば、新しい事業にたくさんの投資をするよりも、安全な国債を買うことで損失のリスクを完全に避けることができます。ただし、大きな利益を得る機会も失う可能性があることに注意が必要です。
二つ目は、危険の芽を小さくすることです。危険が起こる確率や、危険によって受ける影響を小さくします。例えば、火事が起きる危険に備えて防火設備を導入したり、従業員に防火訓練を定期的に実施することで、火事が起きる確率や火事による被害を小さくすることができます。
三つ目は、危険を他の人に負ってもらうことです。保険会社と契約を結ぶことで、事故や災害が起きた際の経済的な負担を保険会社に肩代わりしてもらうことができます。保険料を支払う必要がありますが、大きな損失から会社を守る効果があります。
四つ目は、危険を受け入れることです。小さな危険や、備えをする費用の方が高くつく危険は、あえて対策をせずに受け入れるという選択もあります。例えば、パソコンの故障といった比較的小さな危険は、そのまま受け入れる判断をすることもあります。
どの方法を選ぶかは、危険の種類や会社の状態によって慎重に判断する必要があります。それぞれの方法には良い点と悪い点があるので、それらをしっかりと理解した上で、会社にとって最適な方法を選ぶことが大切です。また、状況の変化に合わせて定期的に見直し、改善していくことも必要です。場合によっては、複数の方法を組み合わせることで、より効果的な備えとなることもあります。
| 対策 | 説明 | 例 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 危険の芽を摘む | 危険につながる行動を完全にやめる | 安全な国債を買う | 損失のリスクを完全に避ける | 大きな利益を得る機会も失う可能性がある |
| 危険の芽を小さくする | 危険が起こる確率や、危険によって受ける影響を小さくする | 防火設備の導入、防火訓練の実施 | 火事の発生確率や被害を小さくする | 設備投資や訓練費用が必要 |
| 危険を他の人に負ってもらう | 保険会社と契約を結ぶ | 事故や災害時の保険金受取 | 大きな損失から会社を守る | 保険料を支払う必要がある |
| 危険を受け入れる | 小さな危険や、備えをする費用の方が高くつく危険は、あえて対策をせずに受け入れる | パソコンの故障 | 対策費用が不要 | 損失発生時の自己負担 |
保険の活用

保険は、思いがけない事故や災害、病気など、将来起こるかもしれない様々な危険に備えるための仕組みです。 人生には、いつ何が起こるかわかりません。不慮の出来事によって、大きな経済的負担を強いられる可能性もあります。そのような事態に備えて、保険は経済的な安全網としての役割を果たします。
保険には様々な種類があります。例えば、自宅や家財を守る火災保険、自動車事故に備える自動車保険、病気やケガによる入院や手術に備える医療保険、そして、他人に損害を与えてしまった場合に備える賠償責任保険などがあります。これらの保険は、万一の際に、保険金を受け取ることで、経済的な損失を補填することができます。
保険を選ぶ際には、自分の状況や必要な保障内容をしっかりと検討することが大切です。例えば、持ち家であれば火災保険への加入は必須と言えるでしょう。また、自動車を所有している場合は、自賠責保険に加えて、任意保険への加入も検討する必要があります。さらに、家族構成や健康状態、職業などによって、必要な保障内容も異なってきます。そのため、保険会社や保険代理店の担当者と相談しながら、自分に最適な保険を選ぶことが重要です。
保険料は、保障内容や加入者の年齢、職業などによって異なります。保険料の支払いは、家計にとって負担となる場合もありますが、万一の際に大きな経済的損失から守られることを考えれば、必要な支出と言えるでしょう。また、保険料控除など、税制上の優遇措置も設けられています。
保険は、加入したらそれで終わりではありません。定期的に見直しを行い、必要に応じて保障内容を変更していくことが大切です。例えば、結婚や出産、転職など、ライフステージの変化によって、必要な保障内容も変わってきます。また、新しい保険商品が登場することもありますので、常に最新の情報を把握し、自分に合った保険を選び続けることが重要です。
| 保険の種類 | 保障内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 火災保険 | 自宅や家財を守る | 持ち家 |
| 自動車保険 | 自動車事故に備える | 自動車所有者 |
| 医療保険 | 病気やケガによる入院や手術に備える | 健康への不安がある人 |
| 賠償責任保険 | 他人に損害を与えてしまった場合に備える | すべての人 |
保険の選び方:自分の状況や必要な保障内容を検討し、保険会社や保険代理店の担当者と相談
保険料:保障内容、加入者の年齢、職業などによって異なる
保険の見直し:定期的に見直しを行い、必要に応じて保障内容を変更
